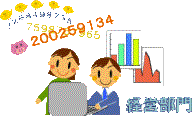三重県亀山市は、県の北中部に位置し、古くは東海道五十三次の宿場町として繁栄した街である。明治に入ってからは国鉄関西線、参宮線の鉄道拠点として、また、国道1号線や東名阪高速自動車道が整備され、名古屋までは40分程度の時間距離になった。現在、第二名神高速道路の工事が進行中で、今後は更に交通の便は良くなるものと思われる。 交通の便が良いことから、工場の進出も多く、大手メーカーの液晶生産工場も建設され、県のクリスタルバレー構想の拠点として産業の集積を図り、先端工業都市としての成長をめざしている。 農業では、米を中心とした農業の他に気候風土を活かしたお茶の栽培が盛んである。畜産農家戸数は、各畜種とも少ないものの肉用牛の1戸当たり平均飼養頭数は、217頭であり、県平均の103頭を大きく上回っている。
(1)労働力の構成
*表中:年齢は平成16年7月現在。労働時間等は、平成15年1月〜12月 *経営主の父の労働:敢えて労働力として本表には表記していないが、経営主の父(93歳)もふれあい農園の維持管理や牛舎周辺の美化(花の手入れなど)に、手を貸している。 また、園児たちが収穫を楽しむイチゴやトウモロコシ、サツマイモなどの日々の肥培管理にも労力を注いでいる。 (2)収入等の状況
(3)土地所有と利用状況
(4)家畜の飼養状況
(5)施設等の所有・利用状況 所有物件
(6)自給飼料の生産と利用状況 該当なし
(1)家畜排せつ物の処理方法 混合処理 (ア) 牛房へおが粉を投入する。この時、戻し堆肥を20%〜30%混ぜる。 (イ) F1と乳用種で日数が異なるが、半月〜1ヶ月で厩肥を発酵槽へ搬出する。 第一牧場の厩肥は、第二牧場の堆肥処理施設へ運搬する。 (ウ) 発酵促進のために、半年以上ショベルローダで切り返す。堆肥舎の床面はブロア付。 頻度は6回〜10回/半年。 (エ) 野菜、お茶、サツキ等の耕種農家へは、3〜4ヶ月(切り替えし回数4〜5回)切り返した堆肥をバラの状態で販売する。マニアスプレッダ散布作業付で9,000円/2t車。配達の場合は、12,000円/2tダンプ 堆肥量の80%がバラ販売。金額では50%である。 (オ) 一般の消費者または小口の農家利用としては、二次発酵させたものを袋詰にする。20リットルものは、主に一般消費者向けとして、35リットルのものは、主に農家向けとして販売する。この販売量は全体の20%であるが、販売金額としては、50%を占める。袋詰めされた堆肥は第二牧場から第一牧場にある堆肥販売所に運搬し、ここで販売する。 (2)家畜排せつ物の利活用
(3)処理・利用のフロー図  (4)評価と課題 1 処理・利活用に関する評価 地域の特性を活かし、耕種農家と連携を取り、野菜、お茶、サツキ農家へ販売している。耕種サイドから要望があれば、マニアによる散布にも対応できる体制である。 過去には、サツキ農家を主な対象としていたため、景気の低迷から公共工事等が減少する中で、販売が思うようにできない時期もあったが、口コミや積極的な販売戦略(楽農祭等での特販等)も効を奏し、順次、堆肥のお客様が固定化できるようになった。 また、ふれあい農園では、堆肥が無料で利用できることも、堆肥利用そのものへの理解が深まり、これも堆肥の固定客を増やすことができる要因となった。 袋詰も20リットル、35リットルに区分し、小口の耕種農家への対応、一般の家庭菜園用等に利用しやすいように気配りしている。 固定客の名簿は耕種農家・一般消費者等を含め現在3,000名を越える規模となった。 2 課 題 耕種農家の利用が基本となることから、季節によっては、堆肥の需要に供給が追いつかない時期ができたり、その逆の時期があることは避けられない。このことから、堆肥の収容能力(収容面積)には、余裕を持たざるを得ない。 季節による需給バランスの是正のためには、新しい販路として、露地物作物ばかりでなく、ハウス園芸作物に目をむけさらに固定客をつかむ努力をしている。 (5)畜舎周辺の環境美化に関する取り組み 第二牧場は、第一牧場(亀山市)から約10km強離れた隣の市(鈴鹿市)にある。この牧場は、水田と茶畑に囲まれた環境の中にあり、周囲の景観そのものに溶け込んでいる。 第一牧場は、市街地からは、約4km程離れた丘陵地域で、県道に面しており混住化も進みつつあり、県道を挟んだ反対側には、マンションも建っている。 こういった環境であることから、牛舎の臭気等で環境問題が発生しないように、牛床は天井扇による送風や早めのおが粉投入などにより、乾燥を保つように工夫と努力をしている結果、牛舎内の臭気対策については問題点はない。 牛舎と県道の間には、概ね300坪の家庭菜園やロバやポニー・ヤギといった小動物が飼われているミニ動物園があり、安らぎを感じられる空間を提供している。 また、農場入り口や道路に面する場所には、パンジーを植えたりして景観の保持に当たっている。花が咲く時期には、カメラマンの被写体になっている。
後継者は、現在29歳で就農以来、既に8年が経過している。中学生の頃から後継者の道を歩むことを決意し、畜産を学ぶために高校・大学と北海道の酪農学園に進んだ。 畜産への道を目指す者が集まった酪農学園での学習は、カルチャーショックとも言えるもので、現在の経営理念に大きく影響を与えたと言える。 「地元に帰って畜産を始めるなら、『三重の豊田』と評価される経営をしたい、地元に根付いた畜産をしたい。」というこの二つが現在の経営理念である。 経営者の妻は、「労働力の構成」で労働時間を示すように、年間家族労働時間9,120時間の21%に当たる1,920時間の労力となっている。その主な作業内容は、導入直後の牛の管理である。ヌレ子を導入していた頃から、導入直後の飼育管理の重要性を充分に認識し、女性の視点で細かい牛の観察や健康のための維持管理に当たってきた。導入月齢が大きくなったとはいえ、現在も導入直後から3〜4ヶ月間の飼育管理が重要であることに変わりはなく、飼育のポイントを任されている。 後継者の妻は、現在3歳児、0歳児の育児に時間を費やさざるを得ない状況であるが、堆肥の小売販売や経理部門を任されている。
(1)地域の農業・畜産の仲間との交流 県内でも当地域は、農業が盛んな地域であり、総体的に後継者も育っており、農業仲間での交流も活発である。豊田畜産では、昨年で4回目となった「楽農祭」を開催していることからも理解できるように、地域の農業者との連携も強い。「楽農祭」は独自で開催するものではあるが、これらの仲間も自らの作物を持ち寄り、販売に花を添えてくれている。 この活動は、長男が所属する「大地の耕作人」というグループが基礎となっている。「大地の耕作人」は、平成14年度に本事業で推薦した養豚事例小林ファームも所属するグループで、定期的にいわゆる青空市場を開催し、地元からの支持を受けている。豊田畜産の場合は、肉用牛経営ということから、この定期的な市場での直販はしていないが、農業に対する志は意気投合するところもあり、このグループ活動に参画している。 (2)地域循環型農業の確立 堆肥を通じて、地域の耕種農家や一般家庭との交流が深い。 長男の就農以前には、地域においてサツキが盛んに栽培されていたが、公共事業の減少など景気の低迷からその需要が減少するのと平行して、堆肥の需要も落ち込んでいった。お茶の生産地域への大口需要を開拓すると共に、販売先(利用先)を家庭菜園やガーデニングといった個人消費に目を向け袋詰め堆肥を提供できるようにした。オリジナル堆肥「ゆたか」の誕生である。 こういった堆肥の顧客にはダイレクトメールを出すなどの努力を怠らず、顧客数は3,000人を上回るものとなっている。 耕種農家に対しては、マニアによる堆肥散布にも応じている。 さらに堆肥部門を発展させる手法をして、堆肥製造販売部門を畜産部門から独立させ有限会社を立ち上げ、事業化している。 (このことから、今回の事例推薦に当たっては、経理上、堆肥部門は別経営として把握するのが本来であるが、別途資料として添付したように、今回の推薦では、畜産部門と合体させた形で報告することとした。) (3)牛舎隣接地に広がるふれあい農園 堆肥を通じてもっと深く一般の人々と交流できないものかと考え実行したのが、長男の就農後に始めたふれあい農園である。牛舎に隣接する約300坪の土地を1区画5坪に区切り、一般の方々に有料で提供しているものである。月500円の使用料で、堆肥と水道は自由に使えるシステムになっている。現在は、全区画が利用されており、申し込みはあるものの順番待ちの状態である。 また、これらの耕作者を対象に、年2回ではあるが、専門家による作物栽培についての現地研修会も開催している。 (4)ミニ牧場や牧場見学の受け入れ 子どもたちにとって、最近の生活環境の中では、家畜や小動物に触れ合う機会がないことから、身近に畜産を感じてもらいたいという想いを持って、ヤギ、ヒツジ、ポニー、ロバなどに直接触れられるミニ牧場を開設し、無料で開放している。敷地内には、飼料タンクを加工したベンチや簡単な遊具も備え、ウィークエンドには賑わいを見せている。 また、近くには小学校3校、中学校2校があることから、学習の一環として肉牛の飼育現場を見学したり、畜産についての話をしたりといったことにも応じている。 (5)消費者との交流とイベントの開催 平成12年に当牧場独自の農業祭として、第1回「楽農祭」を開催した。毎年1回の開催でまだ歴史は浅いが、昨年度、第4回の開催に至った。このイベントでは、地域の農業者仲間らの地域の農産物の販売や牛肉の予約販売などで、終日賑わいを見せる。 企画からダイレクトメールの発送等すべてが手づくりのイベントである。 地場産品の販売だけでなく、昨年度は、クリスマスリースづくりの講習会を開催するなど、イベント内容に幅を持たせている。 消費者とのつながりの重要性を痛感したのは、平成13年に発生したBSE騒動であった。この大きな壁を乗り越えるためには、牛の飼育方法や給与する飼料について正しい情報を提供し、理解してもらえば道は開けると信じ、知り合いの精肉店でパックを作ってもらい販売に結びつけることができた。それまで堆肥販売で交流のあった皆さんに対し、牛肉販売のダイレクトメールを出した。これに対する反響は予想以上に大きいものであった。 (6)後継者の畜産に対する想いを新聞へ寄稿 平成11年10月から翌年3月までの期間に17回にわたり、地元新聞にコラムとして「まきば通信」を寄稿した。畜産について親しみをもってもらいたいという想いから、給与飼料、飼育方法、環境問題、堆肥の利用などについて、一般消費者にわかりやすい表現で執筆にあたった。
現在の経営規模に至るまでの経緯は上述してきたとおりであり、規模拡大も目標に達したと考えている。この規模から生み出される牛肉としての「量」は、満足できるものとなった。 次に目指すのは「質」である。市場取引での評価は現状でも経営上の問題はないが、さらに一人でも多くの方から「豊田の牛肉はおいしい。」といった評価をもらいたいと考えているところである。 しかし、こう言った目標を樹立し、実践していくには、旧態依然とした生産農家であってはならないと考えている。生産に多くの労力を注ぐ農業であっては、その後の発展には限りがあり、また、結果から得られる満足感・充実感にも限度があるように感じる。 経営にとっての満足感・充実感とは、消費者からいただく精神的な面もあるが、事業主としては、やはり注いだ知識や労力、努力に値する適正な所得というものが必要であると思う。もと牛の選定、飼育技術、渉外能力、経営管理能力といった能力を身につけ、研鑽していくことが重要であると考えている。 後継者も、「豊田ブランド」を確立し、一人でも多くの消費者に満足を提供していきたいと考えているが、やはり基本は経営の根幹部分を確固たるものにした上で、その後の展開にもっていくことが正攻法であると思う。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||